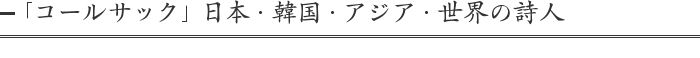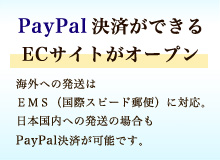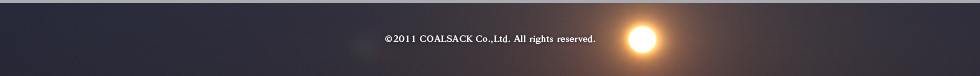<略歴>
1954年 東京生まれ、千葉県柏市在住。
1987年 詩誌「コールサック」創刊。
2006年 株式会社コールサック社を設立し、出版活動を開始。
詩集『風と祈り』『常夜燈のブランコ』『打水』『火の記憶』『呼び声』『木いちご地図』『日の跡』『鈴木比佐雄詩選集133篇』。
評論集『詩的反復力』『詩の原故郷へ―詩的反復力Ⅱ』『詩の降り注ぐ場所―詩的反復力Ⅲ』『詩人の深層探求―詩的反復力Ⅳ』。
日本現代詩人会理事。日本詩人クラブ、日本ペンクラブ、宮沢賢治学会、各会員。鳴海英吉研究会事務局。
(株)コールサック社代表。
<詩の紹介>
ヒマワリ
その町にはいたるところにヒマワリが咲き乱れていた
むすうの見知らぬ瞳から黄色い光が発射されて
転校生は射すくまれたように立ちすくんでいた
その町には樹木が多く蝉がいたるところで鳴いていた
むすうの空気の波動が空から降りてきて
転校生は身体がぐらぐらと揺れてくるのを知った
木造の校舎には冷んやりとした風が流れていた
老教師のあとから騒がしい教室のなかにはいっていくと
子供たちは水着に着替えるのに忙しく転校生など見てはいなかった
そのプールサイドにも大きなヒマワリが咲いていた
水面に映る巨大な黄色い瞳を掻き消して
少年少女たちがプールに吸い込まれていった
水中じゃんけんをしたり、水を掛けあい、勝手に泳ぎまわる
水しぶきと少年少女たちの歓声が蝉の鳴き声と響きあって
ヒマワリの瞳の底の青空に落ちていった
フエが鳴りいっせいに子供たちはプールサイドに上がってくる
水着から滴り落ちる水に転校生の喉はカラカラだった
目の前の水の塊が生きもののようにうねっていた
その町の少年少女の瞳は以前の町よりもひとまわり大きく
サルビヤの蜜を盗んでも叱られない学校だった
フエが鳴り、つぎつぎに少年少女が独力で泳いでいく
水着のないまだ泳ぐことを知らない転校生の目の前
ゆらめく巨大なヒマワリの瞳のさらなる奥へと
花びらが落ちるように黄色い水着の少女が飛び込んでいく
大樹がささやいた
初めて柏駅に降り立った日
近くの野原に 二本の
楠の大樹を見つけた
心を静めないと
聞こえてこないものがある
ああ、きっと樹木語を話しているのだろう
空の青、雲の白さ、鳥たちからの伝言
商店街の人々のかけ声
子供たちの小さな願い事など
噂していたのかも知れない
なだらかな枝振りが緑葉を茂らせて
風にさわいでいた
仲のいい夫婦か兄弟のように
たがいを見守りながら
緑葉をふるわせお喋りをしていた
楠の大樹を見上げながら
この町に住もうと決めた
十年暮らした頃
大樹のある野原が駐車場に変わった
二本の大樹はなだらかな枝を切られて
手賀沼のほとりに新設される
ふるさと公園に移された
手賀沼の朝日が昇り
巨大鉄塔の下
沼風の通り抜ける場所だ
丸裸になった大樹たちは一冬を越した
春、一本の大樹からは芽が出ず
立ち枯れていった
それからまた十年後
立ち枯れた樹木の切り株に目をやり
残された大樹を見上げると
どこからも樹木語は発せられない
目を閉じると
かつて私が朝夕、見つめた
美しい樹影がよみがえる
あの大樹たちがささやく
しなやかな音階に耳を傾け
深い憧れを抱いて通り過ぎた
そんな歳月があったのだ
十五歳の成人式
受験勉強をしていた少年が
その火で火事になり焼け死んだという
朝のニュースが頭からずっと離れない
人はなぜこの寒い世界に 生まれて来るのだろう
二月のみぞれ降る日 焼死した少年を悼み
いつものように駅に着いた私は
今日が何の日だか 思い起こす
十五年前の今日
雪降りしきる秋田の病院で
顔をくちゃくちゃして
大泣きする息子が生まれた
店じまいの直前 駅前のケーキ屋に駆け込み
そそくさと苺ケーキを買い
雪みぞれのなかを帰宅する
胸の病から癒えて 受験勉強をしている息子に
紅茶とケーキでささやかな祝福をしよう
私の十五歳の頃 父が貸した金を返してもらえず
会社を潰してしまった
家族が金によって苦悩するのが分かった年だ
詩らしきものが浮かんできたのもこの頃だった
密かに人間の魂の成人式は、人の世の哀しみを知る
十五歳の頃ではないかと思う
私には三歳違いの十五歳で死んだ弟がいた
弟の生きる苦悩はどんなに深かったか
「兄さん、眠れないんだ」
と呟いた弟の相談相手にもなれなかった
いまも みぞれが雪に変わる空
並木道の裸木の枝に降りしきる
死者たちの棲む雪景色を眺めている
弟の十五歳の誕生日には何をしてあげたか
クリスマスイブの一日前の誕生日だから
きっと母がケーキを買って祝ったはずだ
それから半年後の小雨の日
高校生になった弟は樹木の枝で
生きる時間を切断してしまった
ケーキをナイフで切り取り
十五歳になった息子は
二切れケーキをたいらげ
すぐに机の戦場に戻っていった
二十世紀のみどりご
一九九九年十二月二十一日未明 大内久さん被曝死
ぼく 青い光を見たよ
からだに青緑が染み込んでしまったよ
そろそろ東海村の水辺から
みんなとお別れだね
みどりごになったOさんが
そう語りかけてくる
みどりご
古代韓国語で
ミ(三)ド ル(周)ゴ(児)
三歳の男児のことらしい
ミドルとは
ミ(水)ド ル(石)でもあり
主語の助詞がつくと、ルがイに変化し
ミドリになるという
水中の苔むした石は
緑色にも青色にも見える
あの日のウランが臨界に達し
中性子線を放射した時と同じように
人は川べりで
自然光が当たる美しい青緑色をみるべきだ
あおみどろ(青味泥)をながめるべきだ
Oさんを八十三日間も苦しめたもの
中性子線の青い淵に沈めたものは誰か
原子力行政は「人命軽視が甚だしい」
という医師たちの痛みの言葉を黙殺し
国も電力会社も安全神話の迷路に逃げて行く
二十シーベルトを被曝した
ぼくの壊れたDNAを置いていくよ
ぼくのように被曝した多くの人よ
ぼくらはミ(美しい)ドリ(鳥)の子となって
二十世紀の放射能の森に永遠に閉じ込められたね
妻と子供たちよ、近寄らないで、恐いことだが
この森では二十一世紀の時間が朽ち果てているよ
*李寧煕『天武と持統』(文春文庫)を参考。
シュラウドからの手紙
父と母が生まれた福島の海辺に
いまも荒波は押し寄せているだろう
波は少年の私を海底の砂に巻き込み
塩水を呑ませ浜まで打ち上げていった
波はいま原発の温排水を冷まし続けているのか
人を狂気に馴らすものは何がきっかけだろうか
検査データを改ざんした日
その人は胸に痛みを覚えたはずだ
その人は嘘のために胸が張り裂けそうになって
シュラウド(炉心隔壁)のように熱疲労で
眠れなくなったかも知れない
二〇〇〇年七月
その人はシュラウドのひび割れが
もっと広がり張り裂けるのを恐怖した
東京電力が十年にわたって
ひび割れを改ざんしていたことを内部告発した
二年後の二〇〇二年八月 告発は事実と認められた
私はその人の胸の格闘を聞いてみたい
その良心的で英雄的な告発をたたえたい
そのような告発の風土が育たなければ
東北がチェルノブイリのように破壊される日が必ず来る
福島第一原発 六基
福島第二原発 四基
新潟柏崎刈羽原発 三基
十三基の中のひび割れた未修理の五基を
原子力・安全保安院と東京電力はいまだ運転を続けている
残り八基もどう考えてもあやしい
国家と電力会社は決して真実を語らない
組織は技術力のひび割れを隠し続ける
福島と新潟の海辺の民に
シュラウドからの手紙は今度いつ届くのだろうか
次の手紙ではシュラウドのひび割れが
老朽化した原発全体のひび割れになっていることを告げるか
子供のころ遊んだ福島の海辺にはまだ原発はなかった
あと何千年たったらそのころの海辺に戻れるのだろうか
未来の海辺には脱原発の記念碑にその人の名が刻まれ
その周りで子供たちが波とたわむれているだろうか
日の跡
日の跡を見つめる
日の光と影のはざまに
ぼくは引きずり込まれる
1
苦灰石
古代シルル紀
四億数千万年前
カナダのバーリントン
ナイアガラ渓谷で
ウミユリ類が生きた日があった
その肢体が岩石となって
今は板橋の公園の片隅にある
前を通るたびに
ぼくは、ふいに
ウニやナマコの祖先を想い
時間酔いにめまいする
2
カジイチゴが熟した日だ
少女漫画を読んでいる娘たちを連れだし
野生のキイチゴつみにいく
先客の蟻と羽虫をおしのけ
母の乳房をもぎ取るように
ジャムの空壜が一杯になっていく
刺で顔を傷つけていることも忘れて
苺とは娘たちにとって
草の中にいる母なのだろうか
3
兄さん 眠れないんだ
弟が失踪した日
小鳥の鳴き声が
けたたましかった
少年が樹木に招かれ
死んでいく少年を
小鳥と虫たちだけが見ていた
あの日から
小鳥の鳴き声は
死者のおしゃべり
虫たちは死体をむさぼる
樹木は死者の住みか
七月の緑陰は死者の眼
4
娘の寝るころ電話が鳴る日
母の添い寝を邪魔された娘は
電話に嫉妬する
ボランティアの相談ごと
尽きない長電話に飽きて
娘は母の足元で眠りにつく
今日も電車の中では
携帯電話によって
嫉妬が渦巻いていたな
沈黙を破壊し
会話を不可能にするもの
ディスコミュニケーション
本当の伝達とは何だろうか
5
原家族に病む
それを原家族症と名付けようか
突き詰めると死に至る
姉は父を見取ったあと
酒におぼれた
深夜 電話が鳴った
手首を切ったの すぐ来て
姉の団地へ車を飛ばす
驚きながら どこか冷めていた
コンビニエンスストアでガーゼと包帯を買った日
6
人はほんとうに疲れると
眠れなくなる
ほんとうに弱ると
食べることを拒絶する
嚥下障害
人は水の飲み方さえ忘れる
最悪のことしか思い出さない
血を地へしたたらせた日
姉は薬の力で死んだように眠り
少し正気になって
この世に戻ってきた
7
南千住
ぼくが生まれた町だ
上り電車が止まる
下りの鉄路の脇は
シロツメクサが敷き詰められ
背の高いビロードモウズイカの
黄色い花が天を突き刺すように
立ちすくんでいる
二匹のモンシロチョウが
美しい曲線を描いて
じゃれあっている
この世の天国のように
もう、たまらないんだな
嵯峨信之さんの肉声が聞こえてくる
十薬 昼顔 ノカンゾウ
夏が近づいてきた日
8
コンビニエンスストアに行く
若い女がおむすびを買う
サラダ、ペットボトルを買う
食べることもファッションか
ここは母殺しの場所だ
家族に止めをさした日だ
自動車が父を殺し
テレビが兄を殺し
ゲームが弟を殺し
母と姉はここでいま殺し合いをしている
便利なものは必ず 人を殺すか
9
日の跡には血が点々と落ちている
ぼくは血痕を辿って迷子になった
家族の誰もいなくなった場所で
空の青さを
緑葉の濃さを
大気の移動を
眼球に感じていた
10
そういうもんですよ
浜田知章さんの口癖がよぎった
タンポポ 朝顔 オオバコ
思い出していた
赤子のぼくが立ち上がり
一人で歩き始めた日を
父、母、兄、姉たちがそのことを賛美し
背を押してくれた
日の跡を
黒ダイヤを燃やす原故郷の人
東日暮里に暮らした李秀賢さんへ
夕暮れの一番星がきらめくころ
私は紙と薪で火をおこし
石炭風呂を沸かすのだった
石炭屋の息子だった私は
石炭を黒ダイヤと教えられた
黒々とした化石のような石炭を眺めていると
太古の森の世界に入っていくのだった
いつのまにか真っ暗な空には
むすうの星がきらめき
その一つを見つめていると
眼の前の石炭と同様に
朱色に燃え始めている
星とは夜空に浮かぶ石炭で
それがあんなに美しく燃えていたのだ
ここに銀色のサイクリング自転車がある
持ち主の青年が腰を浮かして漕ぎ出し
韓国の海辺の町 釜山からソウルへ
一陣の風が起こった
彼は韓半島をサイクリング自転車で駆けめぐった
そして日本の富士山をもマウンテンバイクで登った
強靱な足腰は韓日の大地を誰よりも踏みしめていた
彼の祖父は日本の炭坑で働き、曾祖父は日本で死んだ
私の祖父や父は東日暮里の隣の町で石炭を商っていた
彼の祖父たちが掘り出した石炭を
私の父たちは黒ダイヤといって生きる糧にしていた
彼は曾祖父の死んだ国をみたいと思った
祖父たちが働いた炭坑を探したいと願ったろう
そんな日本の地の底に降りていき
韓日の底に流れる未知の鉱脈を探ろうとした
東海(日本海)をこえて
日本列島を東上し
富士山を駈けのぼり
炭坑で働き病み苦しんだ祖父の魂を悼んだ
強制労働させられたアジアの民衆を悼んだ
その時 東から昇る日輪の輝きが彼に何かを促した
それから東方の日の暮れる里(東日暮里)に辿り着いた
東京の下町 夕焼けの美しい町だ
あまたの民衆の眠る墓地のある寺町だ
彼は在日朝鮮人たちが日本人と仲良く暮らす町
新しい窪地(新大久保)という町も好きになった
彼は「韓日の架け橋になりたい」と誓った
「勝利に驕らず/敗者に寛容/確固たる自分を持ち/
後悔しない生き方を宣言できるような/
子どもに育って欲しい」
そんな父母の言葉を彼は想起していた
一台の銀色の自転車がダイヤモンドに変わる
その自転車にまたがった青年は東京の町を走った
鉄路に落ちた迷える酔っ払いを助けるために
日本人カメラマン関根史郎さんと一緒に命を燃焼させた
そしていまも
アジアの夜空にきらめく銀河のように
私たちの頭上で黒ダイヤを燃やしている
李秀賢、関根史郎 あなたたちは
国境を越えた原故郷の人になって
私たちの魂の底を照らし続けるのだ
二〇〇五年一月 四周忌の命日に
花巻・豊沢川を渡って
1
朝靄のなか
花巻駅から一時間歩き
懐かしい豊沢橋を渡って
羅須地人協会跡の
「雨ニモマケズ」碑に向う
明けてくる朱色の空に
ぼんやり乱反射しながら
藍色の雨雲が流れていく
天から光の粒になって降りてくる朝霧と
川面から立ち昇る湯気とが交じり合い
豊沢川付近はまっ白い星雲のただなかだ
土堤に咲く彼岸花や紫詰草の花が赤や赤紫に燃えて
七十五年前にこの橋を渡っていった人の
背中を追って下根子近くまで歩いてきたが
このあたりから松林が見えるだろうか
2
松林の小径を抜けていくと
篝火の焚かれていた広場に出る
碑は朝露にぬれて立ち尽くしている
その下に賢治の分骨と全集が納められてある
二日前の賢治祭がよみがえり
闇に篝火の燃える赤が
むすうに異なった赤色を次々生み出していた
その炎の奥に飛び込んでいきたかった
松林は風に揺れて、鳥たちが騒ぎ出し
下手なピアニカのように染みてきた
「下の畑に居ります」という声がして
松林を抜けて降りていった
3
黄色い穂の稲田がみえる
冷害に強い陸羽一三二号の肥料設計した人は
稲の切っ先をみながらどこかで思案していたか
百姓では食えなくて
「ヒドリノトキハ ナミダヲナガシ」た人は
「ヒドリ」(日雇い)になっていく百姓を
この場所からどんな思いで見詰めていたか
稲田の近くにある野原には
リンゴをたくさん実らせた樹があった
リンゴにあたって死んだ人を記した
ユニークな詩人の畑とはこの場所だったか
落ちていたリンゴを二個拾いポケットに入れた
猛烈な喉の渇きを覚えて
リンゴにあたってもいいから
歩きながら芯まで食べた
あの人の背中はいつのまにか
稲田の黄色い穂先をすべって
五輪峠を越えて
岩手山の方へ消えていった