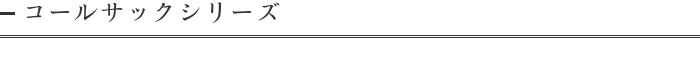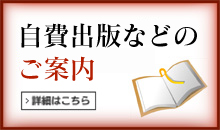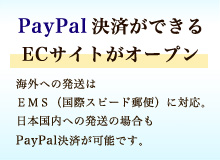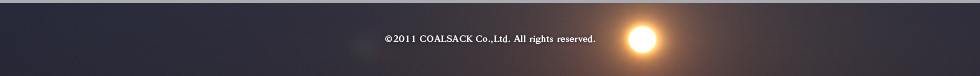佐藤吉一
『詩人・白鳥省吾』
省吾の足跡を探求すること四十年。その事蹟はもとより、単行本や発表誌などの書誌、交遊録、創作(依頼を含め)に至った由縁、作詞した校歌の一覧、刻まれた碑の所在など、実地調査に基づいて収集された労作が、満を持して上梓された。栗駒山を眺めながら伏流水によって育てられた二人の出会い―これを〝相逢〟と言わずに何と言おう。―千葉貢(高崎経済大学教授・博士)解説より
ダウンロード不要の電子ブックが開きます。
その他にも立ち読み可能な書籍がございます
【コールサック社電子ブック立ち読みサイトはこちら】
| A5判/656頁/ハードカバー/ISBN978-4-86435-154-6 C1095 ¥2000E |
| 定価:2,160円(税込) |
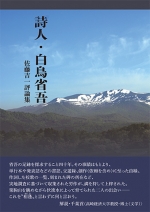
発売:2014年7月2日
【目次】
巻頭 口絵写真・白鳥省吾著作物の一例
目次
はじめに
第一章、 生い立ち 明治二十三年~三十四年(一八九〇~一九〇一)
第二章、中学時代の背景 明治三十五年~四十年(一九〇二~一九〇七)
㈠、旧制築館中学校とその背景 明治三十五年~三十七年
㈡、詩へのめざめ 明治三十七年~三十八年
㈢、二高受験失敗 明治三十八年~四十年
第三章、早稲田大学入学前後 明治四十一年~明治四十三年(一九〇八~一九〇一〇)
㈠、人生の岐路 明治四十一年
㈡、早稲田入学と失恋 明治四十二年一月
㈢、詩壇への一歩 明治四十三年
第四章、第一詩集『世界の一人』出版 明治四十四年~大正三年(一九一一~一九一四)
㈠、詩人としての出発 明治四十四年
㈡、『詩歌』と『劇と詩』 大正元年
㈢、早稲田大学卒業 大正二年
㈣、処女詩集『世界の一人』出版 大正三年
㈤、『世界の一人』の批評
㈥、リアリストの萌芽
第五章、「詩話会」誕生 大正四年~六年(一九一五~一九一七)
㈠、出会い 大正四年
㈡、「詩話会」前夜 大正五年
㈢、対立する新進詩人たち 大正六年
㈣、「詩話会」誕生 大正六年
第六章、 民衆詩派誕生 大正七年(一九一八)
㈠、雑誌『民衆』 大正七年
㈡、「殺戮の殿堂」 大正七年
㈢、民衆詩派誕生の頃 大正七年
第七章、民衆詩派全盛の頃 大正八年~十一年(一九一九~一九二六)
㈠、年刊詩集『日本詩集』発刊 大正八年
㈡、省吾と「ホイットマン詩集」 大正八年五月
㈢、第二詩集『大地の愛』 大正八年六月
㈣、結婚前後 大正九年
㈤、「詩話会」分裂 大正十年
㈥、新作詩集『楽園の途上』 大正十年
㈦、月刊詩雑誌『日本詩人』 大正十年十月
㈧、民衆詩運動第二期と『種蒔く人』 大正十年~十一年
㈨、論争前夜・詩集『共生の旗』 大正十一年
㈩、白秋と省吾の論争 大正十一年
第八章、 民衆詩派の凋落 大正十二年~十五年(一九二三~一九二六)
㈠、関東大震災と「詩話会」の人々 大正十二年
㈡、チブス発病と「詩話会」内紛 大正十三年
㈢、「民衆詩派」の周辺(「山村暮鳥と花岡謙二」「童謡詩人会」「詩壇時評」「駄辨に答へる」)
大正十四年~十五年
㈣、民衆詩派の人々とその評価(百田宗治の「所謂民主詩の功罪」、金子光晴の「大正期の詩人たち」
中西悟道の「詩の三つの姿態」、「菊地康雄・三好達治・遠地輝武・西田勝・古林尚・
瀬沼茂樹の各論」「民衆詩運動の再評価」)
㈤、「詩話会」解散(「詩話会解散前夜」「詩話會解散の経緯」)大正十五年
㈥、石川啄木・宮澤賢治と白鳥省吾
㈦、晩翠先生と「荒城の月」詩碑
第九章、 白鳥省吾論
㈠、「白鳥省吾論」について
㈡、萩原朔太郎の「詩壇時言」
㈢、壺井繁治の「白鳥省吾論」
㈣、松永伍一の「白鳥省吾の位置」
㈤、室生犀星の「白鳥省吾論」
㈥、白鳥省吾の発禁本について
㈦、民衆詩派詩人達の文学賞
第十章、 白鳥省吾主宰詩誌『地上楽園』 大正十五年~昭和十三年(一九二六~一九三八)
㈠、詩誌『地上楽園』について
㈡、「大地舎の事業」
㈢、「詩人倶楽部のこと」
㈣、「大地舎清規」
㈤、「地上楽園の方針」
㈥、「大地舎のこと」「大地舎だより」
㈦、「大地舎」のマークについて
㈧、『地上楽園』バックナンバー
㈨、詩壇の大御所達(須山計一画伯の風刺画)
㈩、珍本 私家版『地上楽園』合本
(十) 一、「大地舎」出版図書
(十) 二、『地上楽園詩集』について
(十) 三、「大地舎」の同人達
(十) 四、「幻の日本女性詩人」C・ハタケヤマ
資 料
㈠、白鳥省吾略歴
㈡、白鳥省吾のペンネーム
㈢、白鳥省吾著書・関連著書目録
㈣、日本全国白鳥省吾作詞校歌
㈤、校歌をたずねて
㈥、白鳥省吾作詞歌謡情報
㈦、日本全国白鳥省吾文学碑・関連文学碑・校歌碑
〝解説〟に上梓の祝意を込めて 千葉 貢
あとがき