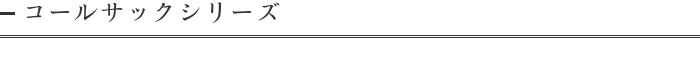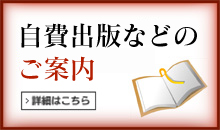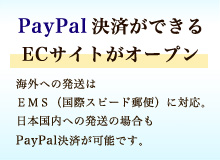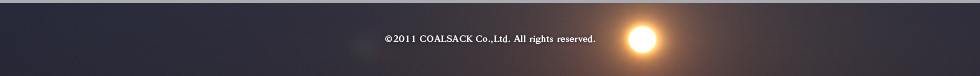書籍一覧 新刊
能村研三随筆集
『飛鷹抄』
新しい年を迎えるにあたり、「沖」に集う皆さんと共に、これからは「人が作らない俳句、人が作れない俳句」をめざし、さらにそれは「人が納得する俳句、人が感心する俳句」でなければならないと思っている。「沖」という組織も、旧態依然のまま甘んじているのではなく、進歩・進展をめざす「沖」でありたい。 (ルネッサンス「沖」より)
ダウンロード不要の電子ブックが開きます。
その他にも立ち読み可能な書籍がございます
【コールサック社電子ブック立ち読みサイトはこちら】
| 46判/172頁/上製本 ISBN978-4-86435-225-3 C1095 |
| 定価:2,200円(税込) |

発売:2015年10月22日
【目次】
第一章「沖」五百字随想
平成十一年(一九九九年)一月~十二月
初日の出 12
職住近接 13
江戸川、船の旅 14
北九州市と俳句 15
市川の文化 16
東山魁夷逝く 17
宗左近宇宙 18
朴の木 19
永井荷風と市川 20
祖母のこと 21
公民館の思い出 22
合掌句碑再訪 23
平成十二年(二〇〇〇年)一月~十二月
五十代へ 24
旅はじめ 25
俳句の英訳 26
父の旅の写真 27
街回遊展 28
同世代の主宰誌 29
能登と能村家 30
作家と記念館 31
水木洋子さんの家 32
私の俳句姿勢 ─ 十年の俳句自分史 ─ 33
平戸・生月の旅 40
焚火と座布団 41
平成十三年(二〇〇一年)一月~十二月
新世紀へ 42
父の成田詣 43
早春の北鎌倉 44
桜のころ 45
人が人を呼ぶ 46
畳のコンサート 47
父の死 48
父の未完句集 49
結社の本卦還り 50
句集『羽化』について 51
市川市民文化賞 52
喪籠りのはずが 53
平成十四年(二〇〇二年)一月~十二月
湾岸の初日の出 54
潔く 55
次世代への文化の継承 56
ITと俳句 57
若手の活躍 58
朴の開花 59
小さなミュージアム 60
声に出して読む 61
白の効果 62
「超割」活用術 63
九月十一日 64
旅つづき 65
平成十五年(二〇〇三年)一月~十二月
雪の降る町 66
俳壇への風通し 67
川柳と俳句 68
登四郎と校歌 69
四月怱々 70
働く者の俳句 71
真砂女さんの思い出 72
岳父の死 73
軽井沢の夏 74
北欧紀行 75
自由に個性的に 76
一年の早さ 77
平成十六年(二〇〇四年)一月~十二月
父からもらった序句 78
地方歳時記の意義 79
小さな町の図書館 80
永井荷風展 81
白い車 82
川柳作家・久良伎の句碑 83
なつかしい原稿用紙 84
井上ひさし先生 85
美術館めぐり 86
月山に登る 87
俳句と読書会 88
母校で語る 89
平成十七年(二〇〇五年)一月~十二月
音楽夢くらべ 90
日だまりの写真 91
編集部の旅行 92
耕二先生の思い出 93
登四郎と湘子 94
きっかけは旅 95
九十九里の前田普羅 96
「沖」の夏 97
全国文学館ガイド 98
パレスホテルの思い出 99
節目の力 100
平成十八年(二〇〇六年)一月~十二月
ルネッサンス「沖」 101
団塊世代と昭和 103
ひとり吟行 104
達人の授業 105
能登羽咋の句碑 106
現場主義 107
二人の朴の木 108
渾身の握手 109
宗左近先生を偲ぶ 110
俳句醸造法 111
秋櫻子・風生と市川 112
文学展の企画 113
モチーフのこだわり 114
平成十九年(二〇〇七年)一月~十二月
新年を迎えて 115
全集の編纂 116
遅筆の信念 117
俳人の訃報 118
「俳句朝日」の休刊 119
俳句と写真 120
国語学会に参加して 121
私の周りの地貌季語 122
吟行の楽しみ 123
代表句をもとう 124
忌日俳句 125
「なづな」の学園 126
平成二十年(二〇〇八年)一月~十二月
一茶のふるさと 127
「まだ八十八…」 128
別の九州 129
水戸の血 130
春欄漫 131
姨捨句碑 132
三つの乾杯 133
合掌句碑十五年 134
この夏―孫の誕生 135
ドイツ・イタリアの旅 136
登四郎特集号 137
雨なら雨を 138
平成二十一年(二〇〇九年)一月~十二月
松山を訪ねて 139
若者不在の俳句 140
俳人の交流 141
三月十日 142
郵便番号「四四四」 143
長寿俳句 144
江東歳時記 145
米沢を訪ねて 146
二十七回忌 147
北九州文学館 148
中原中也と山頭火 149
親交七十年 150
平成二十二年(二〇一〇年)一月~十二月
文化、冬の時代 151
「手児奈文学賞」十年 152
和菓子 153
定年退職 154
哀悼・井上ひさしさん 155
小澤克己さんを悼む 156
ドイツの旅 157
熱い夏 ―四十周年の夏 158
盆僧 159
志を持った結社をめざして
―「沖」創刊四十周年を迎えて― 160
編集長交替 162
「沖晴れ」に勝るもの 163
平成二十三年(二〇一一年)一月~十二月
登四郎生誕百年 164
句集出版 165
水脈・山脈 166
巨大震災 167
井上ひさし先生一周忌に 168
置酒歓語 169
俳人のできること 170
デジタル時代 171
東京吟行 172
募金・チャリティ 173
谷中の曼珠沙華 174
大槌町を訪ねて 175
平成二十四年(二〇一二年)一月~十二月
四十周年から五〇〇号へ 176
成田山詣 177
古参同人の逝去 178
「ご恩回し」の思想 179
『坂の上の雲』の子規 180
五百冊の重み
―「沖」通巻五〇〇号を迎えて― 181
三つの吟行会 183
五〇〇号大会を終えて 184
博多山笠 185
富士山 186
芭蕉通夜舟 187
蓜島正次さんを悼む 188
この一年 ―「編集賞」の受賞 189
平成二十五年(二〇一三年)一月~十二月
「よくばり」のすすめ 190
「俳」活運動 191
老いてなお 192
蔵書の整理 193
季語の比喩 194
十三回忌 195
吟行会の手帳 196
文学ミュージアム 197
書庫のお宝 198
二〇二〇年 199
素材か表現か 200
千葉都民 201
平成二十六年(二〇一四)一月~十二月
和食 202
一字題詠 203
吉報 204
俳句の本の収蔵 205
完全退職 206
「沖」の記念出版 ―季語別俳句集 207
芒種 208
諏訪湖畔 209
市民会館の思い出 210
伯母逝く 211
静岡の勉強会 212
六十五歳 213
平成二十七年(二〇一五年)一月~九月
丁寧に暮らす 214
自註句集 215
谷中のヒマラヤ杉 216
時には他流試合も 217
書斎訪問 218
梅雨の句 219
二つの連載 220
サンディエゴ訪問 221
外房の家 222
第二章「俳句・NOW時評」/「操舵室」
結社の終焉 224
俳人協会と四十代 226
俳人にとっての履歴とは 228
結社から見た総合誌 230
戦後という括り方 232
年下のライバル 234
俳句はやはり頑張るもの 236
仕事と俳句の距離 238
アマチュア化の中の師系 240
「女流」「女流」という時代 242
二十年経った高柳重信のことば 244
実作と評論 246
結社の継続性 248
芽吹きのころ 250
吟行の効用 252
結社のマグニチュード 254
老いを輝かせる 256
二世時代 258
関西の垣根 260
「21世紀を睨む」─新刊書から─ 262
結社・地方との距離 264
「また辛口に」 266
師系について 268
あとがき 270
著者略歴 272